社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~54
2025/08/19
書面によらない贈与契約が成立したことと贈与の履行の事実を疎明させるものとして、
・贈与契約書 署名、押印、各人ごとに印鑑(銀行印も含まれます)を作成等々は他の箇所を参照、同様の論点です。
・通帳間での資金移動
・贈与後は預金管理、キャッシュカード、通帳、証書、印鑑の保持者、受贈者のみが全て把握できる状態で、贈与者は一切関知していないことが理想ということになります。
ハ 停止条件付の贈与
その条件が成就した時
ニ 農地又は採草放牧地の贈与
上記イからハまでにかかわらず、農地法の規定による農業委員会又は都道府県知事の許可のあった日又は届出の効力の生じた日(ただし、その許可に停止条件が付されている場合など、許可のあった日又は届出の効力が生じた日後に贈与があったと認められるものを除く。)贈与の時期がいつであるかは、所有権などの移転の登記又は登録の目的となる財産についても上記と同様に判定しますが、その贈与の日が明確でないものについては、
(証拠)
・特に反証のない限りその登記又は登録があった時に贈与があったもの
として取り扱われます(相基通1の3・1の4共-8~1の3・1の4共-11)。
③実務上のエビデンスとの関係
民法原則の「書面によらないもの」「口頭でも契約は成立」という考え方は租税実務においては全く意味をなしません。書面によるものは、後述の処分証書反証でも有利な証拠となります。最判昭和47年11月8日では、意思表示で足るとしています。
「株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力」
株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
この考え方は法的効果としては意味をなします。しかし、税「実務」という意味では証拠がないから、疎明力がないから、といった理由で全く意味をなしません。贈与は疎明が非常に難しい取引ですから、なおさらエビデンスを当初から拡充しておく必要があります。
(証拠)
・贈与契約書ついては原則として確定日付を付す
・第三者が立ち会ったことについて別書面でよいので覚書を付す
・疎明力としては弱いと考えられますが贈与の意思表示の録音 等々
(3)基本的な考え方、名義財産
名義財産のうち、名義株を前提とします。オーナー企業の相続税対策等のために、株主構成を変更させる場合があります。その方法としては、
①新株の発行・引受
②株式の譲渡(有償譲渡)贈与(無償譲渡)
が考えられます。
しかし、名義株は典型的な当局指摘項目です。相続税法での条文上は相続により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するものとあります。名義株は、この原則からでは、つまり、相続税法の規定を使った否認をする、という理屈は成立しません。上記原則ではなく、相続による財産取得=相続財産の範囲という事実認定に着地します。株式の有償譲渡(売却)無償譲渡(贈与)についての証拠保全はシリーズ<個人編>で解説しています。
〇贈与、売買などの譲渡
契約書締結・株券交付(株券発行会社のみ)(民法176、会社法128)が前提となるため、
→(証拠)
・贈与契約書
上掲のとおり、疎明力を高める努力が必要です。贈与契約書は通帳間を通した金銭のやり取りといった補助的な資料の拡大が非常に困難です。そのため当局調査では時系列や署名押印欄等々を総合的に判断され、バックデイト作成の可能性を必ず念査されます。
重要情報2
(相続財産の範囲/贈与事実の存否) 贈与税の申告及び納付の事実は、贈与事実を認定する上での一つの証拠ではあるが、贈与事実の存否はあくまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきであるとした事例(平19-06-26裁決)TAINSコードF0-3-218
(一部抜粋)
4 判 断
ロ 贈与税の申告事実と贈与事実との関係について
納税義務は各税法で定める課税要件を充足したときに、抽象的にかつ客観的に成立するとされ、贈与税の場合は、贈与による財産の取得の時に納税義務が成立する(通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第5号)とされるが、この抽象的に成立した贈与税の納税義務は、納税者のする申告により納付すべき税額が確定(申告納税方式)し、具体的な債務となる。
このような申告事実と課税要件事実との関係については、「納税義務を負担するとして納税申告をしたならば、実体上の課税要件の充足を必要的前提要件とすることなく、その申告行為に租税債権関係に関する形成的効力が与えられ、税額の確定された具体的納税義務が成立するものと解せられる」(高松高裁昭和58年3月9日判決)と示されていることからすると、贈与税の申告は、贈与税額を具体的に確定させる効力は有するものの、それをもって必ずしも申告の前提となる課税要件の充足(贈与事実の存否)までも明らかにするものではないと解するのが相当である。
そうすると、贈与事実の存否の判断に当たって、贈与税の申告及び納税の事実は贈与事実を認定する上での一つの証拠とは認められるものの、贈与事実の存否は、飽くまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきと解するのが相当である。





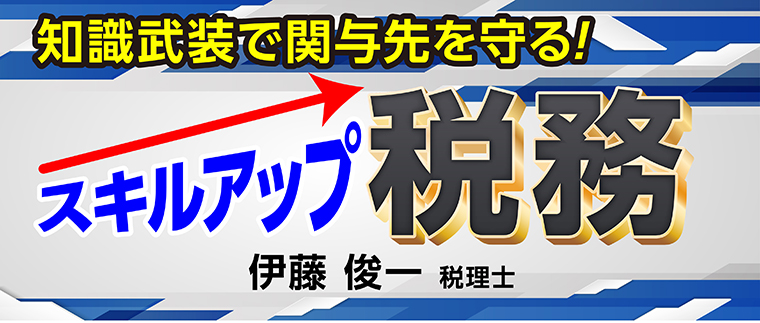




 無料登録はこちら
無料登録はこちら