社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~㊺
2025/03/21
2)
なお、同判決は、債権の回収可能性は、財務内容だけで決定されるものではなく、その借入れを含む資金調達能力や信用力などにも大きく左右される旨判示し、結論において、当該会社が実質的に債務超過状態にあったとしても、事業を現に継続しており、金融機関から新規融資を受ける一方、返済も順調に行われていること等から、回収可能性について疑問を抱かせる事情は認めることができないとして、当該会社への貸付金は額面で評価すべきと判断し、国側が勝訴した事例である。
(2)小括
名古屋地裁判決の上記解釈は、その上級審である名古屋高裁判決においても引用されている。
一方、名古屋高裁判決では、原審を引用する他に、補正として上記2(1)ロの枠囲み部分(債権回収の可能性や程度の検討に当たり、評価時点までの客観的指標、特に、会計帳簿の記載や外形的に明らかな事実を中心に行い、そのような危惧を抱かせる事情が存しないと判断される場合には、これに反して債権の回収可能性に影響を及ぼすべき要因が存在することが的確に窺えないかぎりは(※下線筆者)、評価時点における債務者の業務内容、財務内容、収支状況、信用力などを具体的総合的に検討した上で、その実質的価値を判断するまでもなく、額面のとおりの時価であると評価することが相当(※下線筆者)である旨)の判断を加えている。
すなわち、名古屋地裁判決で判示した解釈について、その上級審である名古屋高裁判決では、条件を付し、より厳格な判断を示しているといえる。
また、名古屋高裁判決及び名古屋地裁判決が示した解釈については、結論において国側が勝訴しておりその処分が取り消されていないため、その上級審において国側が解釈について反論する余地がないものであったと窺える。
4 裁判例を参照する際の留意事項
本件は、納税者と国側が、評価通達の解釈についてそれぞれ異なる裁判例を基に主張を展開したところ、裁判所は国側の主張を採用し、その解釈に基づいて事実認定をした結果勝訴した事例である。今後の調査において裁判例を参照する際は、次のことに留意して調査に生かされたい。
(1)確定しているか
上訴の有無を確認し、上級審により取消し、変更又は破棄がされていないかどうか確認すること。なお、第一審判決、控訴審判決及び上告審判決がある場合には、効率的な読み方は、上告審から読む方法であるが、正確に理解するためには第一審から順に全級審を読む必要がある。
【確認方法】判例等データベース、税務情報データベース等
(2)射程の範囲の検討(裁判所の認定事実と法律的判断の結論を併せて読むこと)
裁判所は、①規範(法令の規定、法令解釈、制度等)を示し、②事実認定を行い、③結論として、認定した事実を規範に当てはめた上で、法的効果を判断している(これを「法的三段論法」という。)。すなわち、裁判所は、常に認定した具体的な事実に基づいて判断をしており、その判断は事実に即したものである。したがって、判決文は、結論だけでなく、認定された事実関係をよく精査し、その判決の射程について検討する必要がある。(※下線筆者)実務ではほぼ遭遇しませんが、仮に前提事実が全く(ほぼ)同じで、争点も全く(ほぼ)同じという裁決・裁判例があれば、先述の先例価値の有無は後回しで検討してもよいです。しかし、当局は上掲のように意識しており、これは納税者でも同様の意識を持つことが必要になります。
筆者が士業から租税法ご相談業務を執務していると、たびたび近似の事案で納税者の主張が認められた裁決・裁判例はないか、と聞かれます。確かに近似の事案での納税者主張が認められたケースは場合によっては存在します。しかし、先ほどからの理由でそれがそのまま当局反論への証拠として成立するか、については原則としては成立しない可能性が高い、と申し上げております。この辺りは弁護士の案件へのスタンス(平たく言えば、自身は法文をこのように解釈しているのでこのように主張する、結果は裁判所が判断することだ、というスタンス)と税理士の案件へのスタンス(平たく言えば、法文、通達等々の規範どおりに執務しないと原則として当局は認めない、自身の独自の解釈論等々は無意味というスタンス)が全く分かれるところです。本書読者は税理士を想定しているので税理士が弁護士スタンスをとることは自身がリスクを負うだけになりますので控えることを強く推奨します。
【参考】最高裁判所民事判例集(民集)に登載された最高裁判決は、最高裁判所調査官による判例解説が、『法曹時報』及び『最高裁判所判例解説(民事編)』に掲載される※ため、当該解説によりその最高裁判決の射程の範囲について検討することが可能である。
例えば、左記の平成22年10月15日最高裁判決は、民集に登載されているところ、最高裁判所判例解説は次のように、本最高裁判決の射程に関する記載があることから、当該解説を参考に、十分にその内容を検討するとよい。
「なお、本判決は、(ア)被相続人が所得税更正処分等に基づき所得税等を納付するとともに同処分等の取消訴訟を提起していたところ、その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を継続し、同処分等の取消判決が確定するに至ったという場合についての判断であって、(イ)被相続人が更正処分等に基づき所得税等を納付して死亡した後に、相続人が同処分等の取消訴訟を提起し、同処分等の取消判決が確定するに至ったという場合については、直接判示するもではない(中略)。」
※これらのほか、当該判例解説のダイジェスト版が『ジュリスト』に「最高裁時の判例」として掲載される。なお、これらの書籍は国立国会図書館等のほか、判例秘書イントラ版(署審理専門官等の審理担当部署が閲覧可能)にて閲覧可能。
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





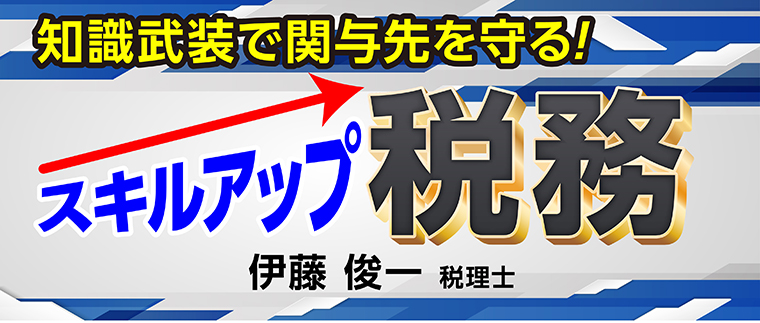



 無料登録はこちら
無料登録はこちら