社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~59
2025/10/16
★1 証拠の観点からは贈与契約書は必須です。金額の重要性から印鑑証明書、確定日付、公正証書等々での準備も必要なケースがあります。なお、先述のとおり、申告書はそれほど証拠力を有しません。
★2 多額の現預金(他の財産もそうですが)が異動する場合、何かしらの本人同士の動機があるはず、としています。これも金額の重要性によりますが、重要性高い金員異動についてはその当時の通帳へのメモ、当事者における日記や手帳等々で記録があれば望ましいです。子供のライフイベントについて親が贈与である場合などは、ライフイベント関係の記録は残しやすいですし、証拠力としても高いです。
★3・★4 名義預金判定の定型文です。これに対する対応は先述のとおりです。
★5 契約書が真正である限り、当該契約書の取引行為自体を否認することは当局も困難であると認識しています。だからこそはじめに契約書がなければ、事実認定で争う土台に立てない、といえるわけです。特に同族特殊関係者間(法人、個人問わず)では必須です。原則として、いかなる取引においても必要となります。(相続財産の範囲/贈与事実の存否) 贈与税の申告及び納付の事実は、贈与事実を認定する上での一つの証拠ではあるが、贈与事実の存否はあくまでも具体的な事実関係を総合勘案して判断すべきであるとした事例(平19-06-26裁決)(F0-3-218)において国税不服審判所判断では、
「(2) 法令解釈イ 親権者が未成年の子に対して贈与する場合の贈与契約の成立について贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となる(民法第549条《贈与》)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから★1親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解される。」
「(イ) 贈与契約書の作成について請求人は、本件株式の贈与について贈与契約書を作成していない点について、本件被相続人は請求人が本件株式の贈与に係る申告をして納税をすることで、その贈与事実を証明することが十分であると考えて、あえて、贈与契約書を作成しなかったものと思われるが、かかる贈与の実態は、親子の関係では、社会通念上、むしろ一般的ではないかとも考えられる旨主張する〔前記3の(1)のイの(ハ)〕。
しかしながら、本件は、親権者と未成年の子との間の契約で、親権者自身が贈与者と受贈者の立場を兼ねていることから、対外的には贈与契約の成立が非常に分かりづらいものとなることは容易に認識できることであり、かえって、このような場合には、将来、贈与契約の成立について疑義が生じないよう契約書を作成するのがむしろ自然ではないかと考えられるほか、平成11年及び平成12年の本件会社の株式の贈与について贈与契約書を作成している〔前記1の(4)のハの(ロ)のBの(B)及びCの(B)〕ことと整合しない点を併せ考えると、上記請求人の主張は直ちに採用することはできない。」とあるように作成「しないほうがむしろ不自然」、と述べています。実務ではこれを勘案し当然作成を行います。
★1
民法549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。親権者が未成年の子に対して贈与する場合の贈与契約の成立について贈与契約は諾成契約であるため、贈与者と受贈者において贈与する意思と受贈する意思の合致が必要となります(民法549《贈与》)が、親権者から未成年の子に対して贈与する場合には、利益相反行為に該当しないことから親権者が受諾すれば契約は成立し、未成年の子が贈与の事実を知っていたかどうかにかかわらず、贈与契約は成立すると解されます。
なお、後々の争い(親族間、税務調査)を回避するよう下記を徹底します。
○ 贈与者の住所、氏名は贈与者が自署する
○ 法定代理人(父、母)の住所、氏名は父母各人が自署する
○ 日付けは贈与者が自分で書く
→ 公証役場で確定日付の印を押してもらうとベスト
→ 確定日付については下記(出典:日本公証人連合会ホームページ)を参照。
「Q 公証人が付する「確定日付」とは、どのようなものですか。
A 確定日付とは、文字通り、変更のできない確定した日付のことであり、その日にその証書(文書)が存在していたことを証明するものです。公証役場で付与される確定日付とは、公証人が私書証書に日付のある印章(確定日付印)を押捺した場合のその日付をいいます。文書は、その作成日付が重要な意味を持つことが少なくありません。したがって、金銭消費貸借契約等の法律行為に関する文書や覚書等の特定の事実を証明する文書等が作成者等のいろいろな思惑から、その文書の作成の日付を実際の作成日より遡らせたりして、紛争になることがあります。確定日付は、このような紛争の発生をあらかじめ防止する効果があります。」
「Q 公証人による確定日付付与の効力は、どのようなものですか。
A 確定日付の付与は、文書に公証人の確定日付印を押捺することにより、その文書の押捺の日付を確定し、その文書がその確定日付を押捺した日に存在することを証明するものです。文書の成立や内容の真実性についてはなんら公証するものではありません。」
この点、文書の内容である法律行為等記載された事項を公証する「公正証書」や、文書等の署名押印などが真実になされたことを公証する「認証」とは異なります。これらは義務ではありませんが、上記の通り、後々の争いを保全するために、自署すべき部分は自署しておいたほうがいいでしょう。
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





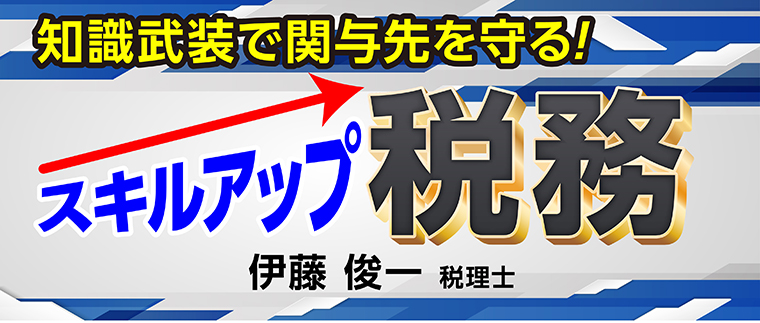




 無料登録はこちら
無料登録はこちら