生命保険税務について最近気になること
2026/02/05
税理士の追中徳久(おいなかのりひさ)です。大学卒業後に新卒で入社した会社が生命保険会社でした。実家の相続の関係で働きながら税理士資格を取得した後も、また、会社を退社した後も、資産税の他に生命保険税務の質問を受けることが多く、今でも年間3,000件を超える生命保険税務のご相談をいただいています。その多くは通達やFAQから明確に読み取れない隙間についてのご相談なのですが、悩みながらした回答を出版などの形で発表させていただいています。
生命保険税務は、令和になって、令和元年の法人税基本通達の改正による法人契約の保険料の取扱いの変更と、令和3年の所得税基本通達の改正による定期保険や第三分野保険を使った法人から個人への利益移転の抑制という大きな変更がありました。
前者は個別通達を整理して、基本通達として法人契約の定期保険や第三分野保険の保険料の損金算入ルールを、最高解約返戻率を基準に改めました。それまでの個別通達による全額損金や半額損金といった単純な損金算入からの大きな変更でした。
後者は目に余っていた、低解約返戻型定期保険を利用した、低解約返戻期間中の法人から個人への契約者変更による利益移転に歯止めをかけるものでした。
これらの見直しにより、保険加入は節税目的というより、生命保険本来の目的である保障や資産形成となり、生命保険税務の取扱いについても問題が少なくなったと思っていました。それを見事に覆してくれたのが、令和6年6月24日の生命保険協会を経由した国税庁からの注意喚起でした。
国税庁から注意喚起自体は、通達に取扱規定のない法人契約の養老保険(法基通9-3-4)や個人年金(平成2年5月30日個別通達)保険料の類推適用への警告、いわゆる養老保険や年金保険を使った逆ハーフタックス契約(契約者:法人、被保険者:役員、死亡保険金受取人:法人、満期保険金受取人:役員、平成24年1月13日最高裁判決参照)の保険料の取扱いを、通達に規定がないのに安易に類推適用して、保険料を全額損金扱することへの警鐘でした。率直に言って、保険税務の現場では、保険契約の新規販売を中止しても、契約者変更を使ってまだこんな恣意的な通達解釈が続いていたのかと愕然とする思いでした。税務調査で損金否認されても仕方ないし、その後、保険会社からの新商品について、保険約款で契約者変更を制限する動きがあったのも仕方ないと思いました。
同時に、ここ数年、低解約返戻型終身保険の契約者変更の可否について、質問が増えていたことも気になりました。令和3年の所得税基本通達36-37の改正は、法人税基本通達9―3-5の2の低解約返戻型の定期保険や第三分野保険に限定して、解約返戻金の額が資産計上額の70%未満だと資産計上額で時価評価するとして、契約者変更を利用して法人から個人に利益移転することを抑制しました。しかし、そこには法人税基本通達9-3-4を準用する低解約返戻型終身保険がすっぽりと抜けて隙間ができていました。現在、この商品の販売自粛をしている大手保険会社もありますが、仮に税法だけは、解約返戻金の額での契約者変更は問題ないと回答せざるをえません。たとえ、一時払低解約返戻型終身保険を法人で契約して低解約返戻期間に個人に契約者変更をするような場合も同様です。
しかし、周辺の行政官庁の規制を確認すると、低解約返戻型終身保険も含めて低解約返戻期間での契約者変更を法人から個人への特別の利益供与の可能性があるとした厚生労働省の「持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度Q&A」Q4-8がありました。また、「生命保険金は、受取人が法人であっても、その性格から最終的に被保険者(あるいはその家族)に渡る可能性が大きいので、私的経費の性格が強い」として、「補助金を受けている学校法人の私的費用を好ましくないという観点から指導している」と、広く法人での生命保険加入を好ましくないとする埼玉県の学校法人会計質疑応答集7-5-1もありました。生命保険は行政官庁からこんな厳しい見方をされているのか、と改めて思いました。
税理士は顧客の取引を経理処理する責務があります。ただ、法令や通達に網羅性を求めるのは難しいとは思います。しかし、われわれ税理士は根拠がなければ所轄税務署に照会しながらでも対応が必要です。できたら、低解約返戻型終身保険のように疑義が発生する事案については、安定的な対応方法を通達やFAQなどで明確にしてもらいたいと思います。
解説/追中徳久税理士





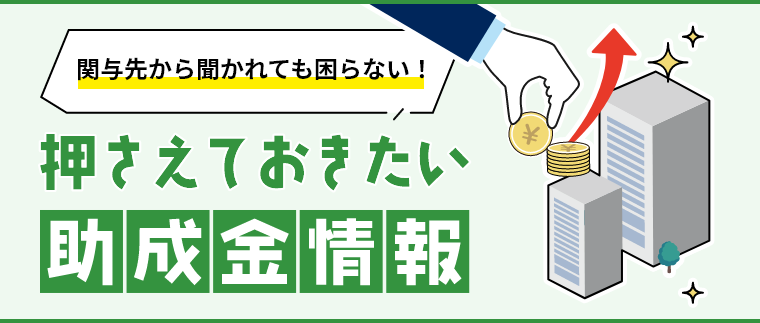

 無料登録はこちら
無料登録はこちら