社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~㊼
2025/04/24
(参照)印紙と契約書に係る諸論点
永井徳人・他『契約書に活かす税務のポイント―比べて分かる基本とスキーム選択・条文表現』中央経済社(2016/ 3/24)該当箇所を適宜参照しています。
〇契約金額変更
・増減額の記載…増額の場合、それに応じて印紙税決定、減額の場合、印紙税の課税文書に非該当
・増減額が記載内容から算出できる場合…上記と同じ取扱い
・契約後の金額のみ分かる場合…契約後の金額で印紙税決定
すなわち、増減額(差額)で判定した方が印紙税は安く済むので有利です。
〇消費税の記載下記では実務でOKなものには一番頭にOK印を付しています。
・内税、外税記載なし…税込金額で決定
OK・外税で消費税額の記載なし…税抜価格で判定
OK・内税で消費税額の記載あり…税抜価格で決定
OK・内税・外税の金額併記…税抜価格で決定
・内税で消費税率記載あり…税込価格で決定
・内税で消費税額の記載なし…税込価格で決定
〇課税事項と不課税事項の混在
・代金内訳あり…当該内訳に応じて判定
・代金内訳なし…契約金額全体に応じて判定
〇複数の課税事項を含む場合
・2つ以上の課税事項含む契約書はいずれか1つにより判定
…それぞれの契約金額を比較し最も大きい契約に係る金額で判定
・内訳ない場合
…契約金額全体で判定
〇契約書の原本とコピー
契約書原本は2通作成せず、1つをコピーとすれば印紙税の節税になります。
Q 持分会社を活用した相続税節税のプランニングについてご教示ください。
下記のようなプランニングですが、実効性に疑義があります。合名会社等の無限責任社員の会社債務について債務控除の適用の可否の論点です。
合名会社、合資会社の場合で、会社財産で債務を完済することができない状態で無限責任社員が死亡した場合、その死亡した無限責任社員が負担すべき、持分に応じた会社の債務超過額は、相続税の計算上、被相続人の債務として相続税法第13条の規定により相続財産から控除することができるか、について、国税庁は、被相続人の債務として控除して差し支えないと答えています。
合名会社の財産だけでは会社の債務を完済できないときは、社員は全員が連帯して会社の債務を弁済する責任を負うとされ、退社した社員は本店所在地の登記所で退社の登記をする以前に生じた会社の債務に対しては責任を負わなければならないとされているため、というのが理由です。無限責任社員が複数いる場合において債務超過である場合については、会社法580条を参照します。当該持分会社の財産をもってその債務を完済できなかった場合には、無限責任社員が無限に連帯して責任を負うことになっております。
この責任については、出資の多寡は問われていないため、会社に財産がない場合、債権者は社員一名に全ての請求をすることができます。
ただし、連帯責任となっておりますので、他の社員に代わって弁済を行った社員は他の社員に対して自己の責任を超える範囲について求償を求めることができます。自己の責任の範囲は無限責任社員数により変動いたします。
【質疑応答事例】
合名会社等の無限責任社員の会社債務についての債務控除の適用8
〔照会要旨〕
合名会社、合資会社の会社財産をもって会社の債務を完済することができない状態にあるときにおいて、無限責任社員が死亡しました。この場合、その死亡した無限責任社員の負担すべき持分に応ずる会社の債務超過額は、相続税の計算上、被相続人の債務として相続税法第13条の規定により相続財産から控除することができますか。
〔回答要旨〕
被相続人の債務として控除して差し支えありません。合名会社の財産だけでは、会社の債務を完済できないときは、社員は各々連帯して会社の債務を弁済する責任を負うとされ(会社法580)、退社した社員は、本店所在地の登記所で退社の登記をする以前に生じた会社の債務に対しては、責任を負わなければならない(会社法612①)とされています。
【関係法令通達】
相続税法第13条第1項
会社法第580条、第612条第1項
1人株主会社があったとします。実態貸借対照表で実質債務超過の会社です。これを組織変更して1人合名会社にします。当該法人はオーナーからの貸付金があり、オーナーの相続財産において券面額で資産計上されることになります。債務超過相当額は債務控除にあてます。結果、相続財産が減少します。または1人合名会社がある場合、これを債務超過の株式会社と合併すると債務超過にするという手法もあります。 一方で、同族法人においては相続発生時に実質債務超過という実態だけでは財産評価基本通達205項は発動しません。
相続税申告時においてオーナー貸付金(会社借入金)は単なる実態貸借対照表ベースでの債務超過、経営不振等でも一切、減価することはできません。にもかかわらず、当該プランニングを利用すると、もともとの制度趣旨が違うため(上記の質疑応答事例は会社法の原則的な考え方から導かれるものです。)、減価できてしまいます。
制度趣旨が異なるため平仄を合わせる蓋然性は全くないものの、根拠法文が違う、つまり、かたや財産評価基本通達(通達のため法文ではありません)、かたや会社法と、異なる使い分けをするのみで減価されるのは私見では腑に落ちません。
【財産評価基本通達205項】(貸付金債権等の元本価額の範囲)
205 前項の定めにより貸付金債権等の評価を行う場合において、その債権金額の全部又は一部が、課税時期において次に掲げる金額に該当するときその他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるときにおいては、それらの金額は元本の価額に算入しない。
⑴ 債務者について次に掲げる事実が発生している場合におけるその債務者に対して有する貸付金債権等の金額(その金額のうち、質権及び抵当権によって担保されている部分の金額を除く。)
(中略)
ヘ 業況不振のため又はその営む事業について重大な損失を受けたため、その事業を廃止し又は6 か月以上休業しているとき
(中略)
上掲ヘが実務上は適用できないか、と疑義が生じるところになります。しかし、上掲をもって係争機関で納税者が勝った事案はありません。私見ですが、当該通達は例示列挙通達ではなく、限定列挙通達になるのではないかと、過去の裁決・裁判例から読みとれます。





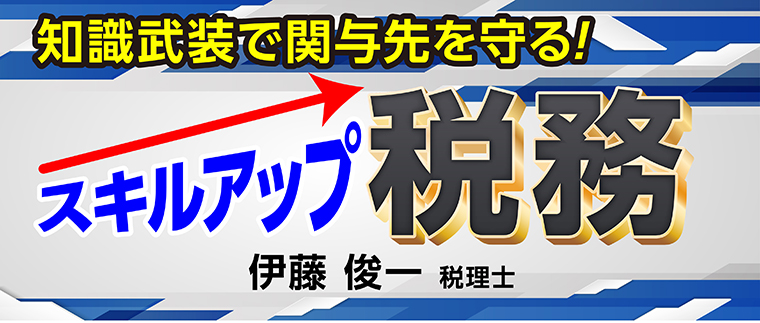




 無料登録はこちら
無料登録はこちら