社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~56
2025/09/09
(裁判所の判断要旨)
1 財産の帰属の判定において、一般的には、当該財産の名義が誰であるかは重要な一要素となり得るものではあるが、我が国においては、夫が自己の財産を、自己の扶養する妻名義の預金等の形態で保有するのも珍しいことではないから、妻名義預金等の帰属の判定において、それが妻名義であることの一事をもって妻の所有であると断ずることはできず、諸般の事情を総合的に考慮して判断する必要がある。
2 乙名義の預金等の取引の手続は乙が行っていることが認められるが、甲所有の預金等についてもその取引の手続を乙が行っていたこと、証券取引の説明には甲も同席していたこと、乙が甲に知らせることなく独自の判断で取引を行っていたことを認めるに足る的確な証拠がないこと等を総合すると、乙名義の預金等の取引は、乙がその手続を行い管理運用していたといえるとしても、その管理運用は甲の包括的同意あるいはその意向を推しはかってされたものと認められる。
3 一般に、財産の帰属の判定において、財産の管理運用を誰がしていたかということは重要な一要素となり得るものではあるが、夫婦間においては、妻が夫の財産について管理運用をすることがさほど不自然であるということはできないから、これを殊更重視することはできない。
4 原告らと乙との関係は相当険悪であったことが認められ、そして、甲と乙の年齢差も考慮すると、甲が、自分の死んだ後に乙が金銭的な面で不自由をしないように、本件遺言書の作成とは別に、自己に帰属する財産を妻名義にしておこうと考えたとしても、あながち不自然とはいい難い。そうすると、実際に生前贈与をした土地建物の持分については贈与契約書を作成し、乙が贈与税の申告書を提出していたのと異なり、乙名義の預金等についてはそのような手続を何ら採っていないことも考慮すると、甲所有の預金等を乙に対して生前贈与したものと認めることはできない。
5 乙が乙名義の預金等を解約して他の用途に使用するなどしたという事情がうかがわれないことからすると、乙名義の預金等から生じた利息の一部が、乙所有の預金口座に入金されていたとしても、乙名義の預金等自体については、甲に帰属していたと認められる。
6 贈与契約書が作成されず、贈与税の申告がされなかったからといって直ちに贈与がなかったとはいい難いが、贈与契約書が作成されず贈与税の申告もされていないことが、贈与の具体的日時の特定を困難ならしめているうえ、贈与の事実そのものを否定する事情の一つにはなり得るものであることは否定できない。
(裁判所の判断のポイント)
実務において、ある財産が相続財産となるかどうか(あるいは贈与されたものかどうか)の事実認定については、その当事者が血縁関係や内縁関係にあるなど、特殊関係者間で行った行為を基に判断するケースがほとんどであり、通常、真実を把握することは容易ではなく、その財産が誰に帰属するかの判定は、非常に困難であると思われます。
この点に関し、本判決の判示事項は、財産の帰属の判定を行うに当たって非常に参考となるものですが、その中でも、実務上、特に参考となるポイントは、次のとおりと思われます。
1 他人名義となっている財産が誰に帰属するかの判断要素
裁判所は、上記「裁判所の判断要旨」のとおり判断していますが、本判決では、その前提として、被相続人以外の者の名義である財産が相続開始時において被相続人に帰属するものであったか否かは、①当該財産の購入原資の出捐者、②当該財産の管理及び運用の状況、③当該財産から生ずる利益の帰属者、④被相続人と当該財産の名義人並びに当該財産の管理及び運用をする者との関係、⑤当該財産の名義人がその名義を有することになった経緯等を総合考慮して判断するのが相当である、と判示しています。
すなわち、裁判所は、被相続人以外の者の名義となっている財産が誰に帰属するか、言い換えれば、ある財産が相続開始前に、被相続人からその財産の名義人に贈与されていたかどうかは、上記①~⑤などを総合考慮して判断するのが相当であるとしているわけです。したがって、名義預金等として相続税等を課税する場合は、この観点を踏まえた聴取調査等の各種調査を行うことが必要であり、そして、その調査によって得られた事実を総合勘案して、課税の可否を判断することが重要かつ不可欠と言えます。
2 財産が誰に帰属するかを判断する上で、財産の管理運用を誰がしていたかは重要な要素ではあるが、それは、帰属の判定上の一要素にすぎない。
上述のとおり、原告らは、一般に、財産を取得する者は自己の名義で取得及び管理するのであるから、財産の帰属先を判定する上で、財産の名義は極めて重要な要素であるところ、乙は乙名義預金等を自らが管理運用していたのであるから、乙名義預金等は乙に帰属する、と主張しました。
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





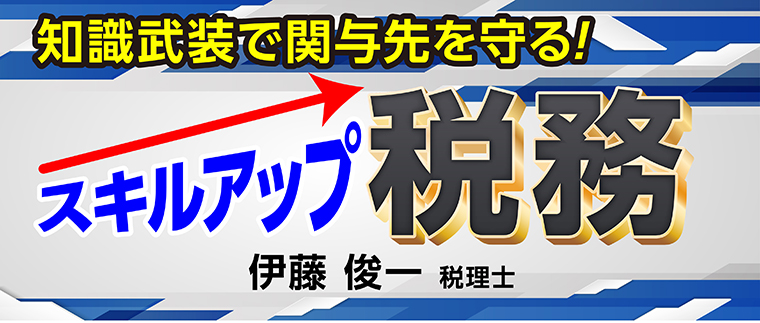




 無料登録はこちら
無料登録はこちら