社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~㊶
2025/01/30
2)
重要情報1
調査に生かす判決情報
~判決(判決速報№1476【相続税】)の紹介~ 平成30年9月27日
《ポイント》
裁判例を参照する際の留意事項
~財産評価基本通達205「その他その回収が不可能又は著しく困難でると見込まれるとき」の解釈及び該当性について争われた事例~
〇事件の概要
1 X(納税者)は、平成23年に死亡した被相続人の相続(以下「本件相続」という。)について、被相続人がその夫である亡Aから相続した貸付金債権(亡Aが代表者を務めていた会社に対する貸付金債権であり、亡Aの相続税の申告において相続財産に含まれていたもの。以下、当該会社及び当該債権をそれぞれ「本件会社」及び「本件債権」という。)が存在しないものとして、相続税の申告書を提出した。
2 Y(国側)は、本件債権は被相続人の相続財産であり、その財産の価額は財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)204(貸付金債権の評価)の定めに基づき評価することとなるとして、相続税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ、Xは、本件会社の業務内容や財務内容等の状況からすれば、本件会社から本件債権を回収できないことは明らかであるから、本件債権の価額は、同通達205(貸付金債権等の元本価額の範囲)の定めに基づき評価すべきであり、その価額は零であるなどとして、本訴を提訴した。
〇本件の争点・当事者の主張
1 本件債権は貸付金債権であることから、その評価方法は、評価通達204及び同通達205に基づいて評価することとなるが、国側と納税者側において、概ね次のとおり主張が対立した。(1) 評価通達205の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」の解釈について(争点1)納税者側の主張評価通達205の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するか否かの判断については、評価通達205(1)ないし(3)に定める各事由に準ずるものあって、それと同視し得る事態に当たらない場合であっても、貸付金債権の回収可能性に影響を及ぼし得る要因が存在することがうかがわれる場合には、評価時点における債務者の業務内容、財務内容、収支状況、信用力などを具体的総合的に検討し判断すべきである。
〔主な証拠(根拠)〕
名古屋高裁平成17年6月10日判決
国側の主張
評価通達205の「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、評価通達205(1)ないし(3)の事由と同程度に、債務者が経済的に破綻していることが客観的に明白であり、そのため、債券の回収の見込みがないか、又は著しく困難であると確実に認められるときをいうのであり、評価通達205(1)ないし(3)の事由を緩和したものではない。
〔主な証拠(根拠)〕
東京高裁平成21年1月22日判決
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





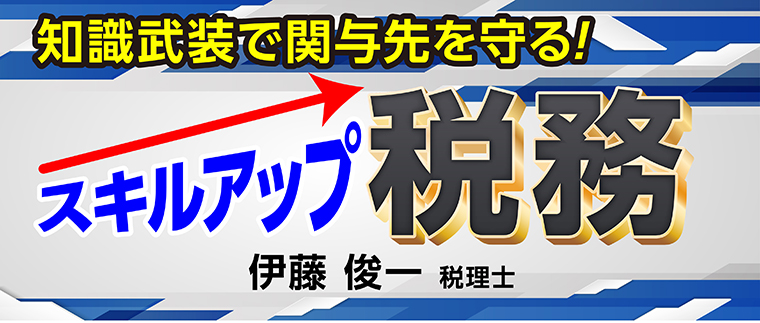




 無料登録はこちら
無料登録はこちら