社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~㊾
2025/05/28
重要情報1
〇大阪地方裁判所平成16年(行ウ)第97号相続税決定処分等取消請求事件、平成16年(行ウ)第141号差押処分取消請求事件(棄却)(控訴)国側当事者・平成16年(行ウ)第97号につき茨木税務署長、平成16年(行ウ)第141号につき大阪国税局長平成18年10月25日判決【相続税法64条1項における「不当に減少」の判断基準/高額な土地取引】
〔判示事項〕
被相続人の遺言書の内容と被相続人と同族会社との間の土地売買契約の内容とが符合しないことなどから、当該売買契約は仮装された存在しないものであるとする課税庁の主張が、当該売買契約書が被相続人の意思に基づいて作成されたものではないと認めるのは困難であるとして排斥された事例。相続税法第64条第1項(同族会社の行為又は計算の否認等)における「相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められる」場合の判断基準。同族会社と被相続人との間で締結された土地売買契約は、経済的、実質的見地において純粋経済人の行為として不自然、不合理なものというほかなく、同社の株主である納税者らの相続税の負担を不当に減少させる結果をもたらすものであることは明らかであるとされた事例。被相続人と同族会社との間の土地売買契約は、当該同族会社を存続させるための唯一の方策として採用したものであり、被相続人らには不当に相続税の軽減を図るという意図など全くなかったから、当該売買契約は相続税法第64条第1項(同族会社の行為又は計算の否認等)により否認することができる場合に該当しないとの納税者の主張が、当該売買契約の究極的な目的が納税者の主張するとおり同族会社を存続させることにあるとしても、時価相当額の13倍をこえる価格を売買契約の代金額として定めることが、経済人の行為として合理的かつ自然なものとは到底いうことはできないのみならず、当該売買契約の締結に至る経過事実に照らしても、当該売買契約が納税者らの相続税の不当な軽減を図ることを目的として締結されたものであることは明らかであるとして排斥された事例。
納税者は土地売買契約に基づき同族会社の借入金債務を承継することになり、それと合わせて相続税等を支払う能力はなかったところ、納税者のように担税力のない者に相続税法第64条第1項(同族会社の行為又は計算の否認等)を適用することは同項の趣旨に反するとの納税者の主張が、納税者が同族会社の借入金債務を負担することになったのは、納税者が代表取締役を務める同族会社が相続税法第64条第1項の規定による否認の対象となるような土地売買契約を締結したことによるのであり、しかも、納税者に同項を適用しないことにより、かえって租税回避行為が容易に行われるのを防止して租税負担の適正化を図るという同項の趣旨、目的が害されることになるとして排斥された事例。
(中略)
同族会社の損益計算書において当期未処理損失が計上され、債務超過状態にあったことがうかがわれるものの、同社について破産、会社更生等の法的整理手続が進行していたり、同社が事業閉鎖により再起不能であったなどの事情はなく、同社は被相続人の死亡後もその事業を継続していたと認められることからすれば、相続開始時において被相続人が同族会社から保証債務に係る求償権の履行を受ける見込みがなかったということはできず、よって、本件における相続債務は相続税法第14条第1項にいう確実と認められる債務には該当せず、相続税の課税価格の計算上控除されないものというべきであるとされた事例(上告棄却・不受理)。相続直前に作為的に債務控除を作出するという点では近似事例と考えられます。
また、下記の裁決においては本件プランニングが争点の1つとなっています。しかし、国税不服審判所の判断においては本件プランニングの是非については一切言及しておりません。TAINSの表題でも(更正の理由附記/処分の理由不備)とあるように税務調査の裁決です。当該裁決を参照とした本件プランニングの是非に係る考え方は一切関係ありません。
なお、「債務を含む会社財産の評価時期は、会社債権者の請求の時であり、会社の債務超過の立証責任は、会社債権者にあるとされている。」と当局は主張しておりますが、同族特殊関係者間法人(個人)においてはこれがさらに厳密に見られます。詳細はシリーズ<法人編>で解説しています。
重要情報2
(更正の理由附記/処分の理由不備)更正等通知書に記載された債務弁済責任に係る債務控除に関する処分の理由には不備があり、各更正処分のうち、債務控除に係る部分は、行政手続法第14条第1項に規定する要件を満たさない違法な処分であるから、取り消すべきであるとされた事例(平26-11-18裁決)F0-3-398
〔裁決の要旨〕
1 本件は、審査請求人らが、被相続人には会社の無限責任社員として負っている会社法第580条第1項に規定する「債務を弁済する責任」があるとして、相続税の課税価格の計算上、「債務を弁済する責任」を債務として控除して相続税の申告をしたところ、原処分庁が、被相続人は「債務を弁済する責任」を負っていたとは認められないから、「債務を弁済する責任」を債務として控除することはできないなどとして、相続税の更正処分等をしたのに対し、請求人らが、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
2 争点は、①本件各処分の理由は「不利益処分の理由」として十分な記載といえるか、②本件債務弁済責任は、「相続開始の際現に存するもの」に該当し、かつ「確実と認められるもの」に該当するか否か、③本件各賦課決定処分について各更正処分が、従来の公的見解を変更してなされたものとして、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するか否か、である。
3 本件各更正通知書の「処分の理由」欄の記載からは、本件相続開始日における債務弁済責任に基づく債務が現に存しないと原処分庁が判断した理由が、例えば、①本件合資会社に14億0,181万6,220円の債務超過額が存しない、②本件被相続人が無限責任社員でない、③本件合資会社の債務超過額はおよそ無限責任社員である被相続人の債務ではない、④本件合資会社の債務超過額は無限責任社員の債務ではあるものの、本件においては、会社法第581条第1項に該当する社員の抗弁の事実があり、無限責任社員の債務として認められるための要件を満たしていない、⑤そもそも、会社法第580条第1項は、債務を弁済する責任を規定しているにすぎないという法律的な見解を前提として、会社債権者からの弁済請求を受けていない以上、本件被相続人は本件債務弁済責任に基づく債務を何ら負っていないなど、様々な可能性が考えられ、原処分庁による処分の実際の理由が、これらのどれに当たるのか、あるいはこれら以外の理由なのか、不明であるといわざるを得ない。
4~7 省略
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





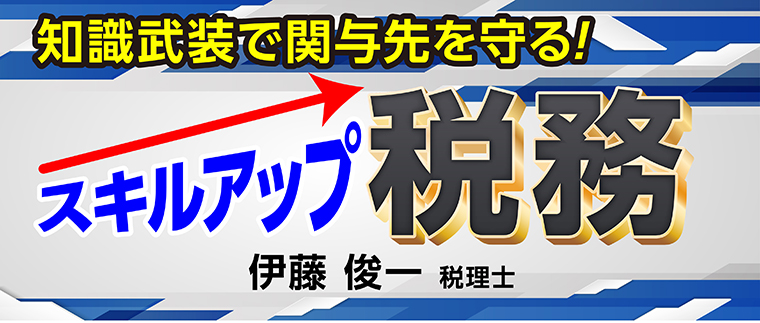




 無料登録はこちら
無料登録はこちら