社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~52
2025/07/14
贈与契約の特徴です。
・対価を伴わない無償契約であること
・対価的関係に立つ債務を負担しあう関係にはなく、一方のみに債務の発生する「片務契約」であること
・当事者の合意だけで成立する「諾成契約」であること
続けて贈与の効力です。
・財産移転義務があること
・担保責任があること(民551)
・負担付贈与も有効であること
① 贈与者は負担の限度において売買における売主と同等の担保責任を負うことになります(民法551②)。
② 負担付贈与は、双務契約の適用があり(民法553)、同時履行の抗弁権(民法533)や危険負担(民法534 ~ 536)、負担の不履行における解除(民540)が適用されることになります。
付随論点として民法1030条と1039条の違いがあります。どちらも遺留分減殺請求に関する条項ですが、
1030条➡無償の贈与に関する規定
1039条➡不相当な対価での有償行為に関する規定
とまとめることができます。そうなると、
1030条➡無償の贈与に関する規定
贈与はそもそも無償なので単純に無償行為と読み替えが可能なのか?
1039条➡不相当な対価での有償行為に関する規定
不相当な対価を受け取っているということはそもそも有償なので低額譲渡(税務上はみなし贈与が認識される)による贈与部分(上記と同様、その部分の無償行為)と読み替え可能なのか?
すなわち、「両者とも無償部分に対する減殺分を取り返すことができると平たく読み変えることは可能か?」という疑問が湧きます。しかし、これより、1030条の規定の適用を回避するために有償行為を装った場合の規定が1039条である、という整理のほうが正確です。
(2)租税法上の贈与
① 租税法上の贈与とは
みなし贈与財産は課税対象となります。相続税法においては、民法上は、贈与により取得したものではない財産であっても、実質的には贈与により取得した場合と同様の経済的効果を持つ次の財産については、課税の公平を図る観点から贈与により取得したものとみなして、贈与税の課税対象としているからです。
租税法では、贈与契約がなくても贈与税の課税関係が生じることはあります。贈与税は、当事者間において民法上の贈与契約があったときにかかる税金ですが、この契約がなかったとしても実質的に贈与したのと同様な効果を生じる場合、例えば、
・受取人が保険料の負担をせずに受けた生命保険契約等の受取金
・掛金等の負担をせずに取得した定期金受給権
・低額で譲り受けた場合の適正価額(時価)との差額
・債務免除、債務引受け又は第三者債務の弁済による債務額
・適正な対価を支払わずに取得した、あるいは、受益者等が存しない場合又は存しないこととなった場合に取得した信託受益権
・その他の経済的利益の享受については贈与があったものとみなして贈与税を課税するとしています(相法5~9の6)。
しかしながら、法律の不知やうっかりということが少なくないことから、自己の財産を他の者に名義変更登記等をしてしまった、他人名義により不動産、船舶、自動車又は有価証券の取得、建築又は建造の登記等をしたことが、過誤に基づき、又は軽率に行われたものであり、かつ、それが取得者の年齢その他により確認できるときは、これらの財産に係る贈与税の最初の申告もしくは決定又は更正の日前にこれらの財産を本来の取得者等の名義とした場合に限り、これらの財産は贈与がなかったものとして取り扱うとしています(直審(資)22(例規)直資68(例規)昭和39年5月23日一部改正昭57. 5.17直資2-177外(例規)名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて)。
このようにこのように、生命保険等の満期受取金の取得や出捐割合と登記持分が異なることによる経済的利益がみなし贈与課税を受ける場合であっても、過誤に気付き贈与税の申告期限前に贈与の取消しや贈与財産の返還、あるいは、課税庁による行政指導として返還や是正を求められたことに従ったものについては、通常は課税処分の発動を差し控えているようです。
なお、贈与契約の取消しや贈与財産の返還に伴う受贈者から贈与者に対する贈与行為については、贈与がなかったものとして取り扱われ、贈与税の課税はされません。
② 贈与の時期
贈与の時期がいつであるかということは、納税義務の成立の時期、その財産の評価の時期、申告期限などに関連して重要な問題となります。
贈与の時期は、次の通りです。
イ 書面による贈与
その贈与契約の効力が発生した時
ロ 書面によらない贈与
その贈与の履行があった時
※伊藤俊一先生の講義は『日税ライブラリー研修』でご受講が可能です。
『日税ライブラリー研修』の詳細・申込はこちら。最新の伊藤先生の研修はこちら。





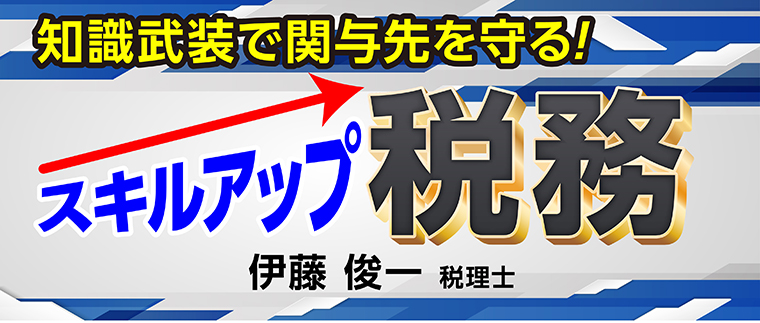




 無料登録はこちら
無料登録はこちら