公益財団法人を作って租税回避を図る
2025/11/14
我が国の公益財団法人の数は約5,900法人、公益社団法人は約4,200法人で、公益社団法人よりも公益財団法人の方が多いのが特徴である。最近の公益認定の状況を見ていると、毎年わずか10名程度の学生に対して一人年間36万円ほどの奨学金を給付する奨学金給付事業を行う一般財団法人や、わずか8名程度の研究者に対して一人年間100万円ほどの研究助成を行う一般財団法人であっても、立派に公益認定を受けられて公益財団法人になっている。

つまり、その程度の奨学金や助成金の財源を確保できる一般財団法人であれば、晴れて公益認定を受けて公益財団法人になれるというわけである。これは相続税対策に頭を悩ませている富裕層にとっては垂涎の的であるといえないだろうか。公益認定は狭き門であったはずだが、こと奨学金給付事業や助成金給付事業を目的とする公益財団法人に対しては、大きく門戸が開かれているように思える。
それで、公益認定を受けていったん公益財団法人になれば、もうしめたものだ。まず、富裕層が寄附という形で保有財産をそこに移転すれば、相続税を簡単に免れることができるだけでなく、寄附税制の優遇措置をたっぷり受けられる。それから、相続人が相続した財産をそこに寄附すれば租税特別措置法第70条の適用で相続税は非課税になる。それがオーナー企業の自社株式などの現物財産である場合、相続税は非課税になって免れたとしても、時価譲渡として譲渡所得税がかかるのが原則だが、これが公益財団法人の場合には国税庁長官の承認を受けて非課税になるいわゆる租税特別措置法第40条の適用のハードルもかなり低くなっている。
それでいて公益財団法人に所有させている自社株式に対しては、影響力を保持することができる。つまり、公益財団法人を所有する仕組みはないので、自社株式の間接保有はできないが、実質的に保有に等しい影響力を行使することはできないわけではない。
これはもう利用しない手はない。役員として理事や監事、評議員が必要だが、そこは地域の名士などを充て、オーナーだけが公益財団法人の理事長に収まって、他の親族を理事にしなければ、公益認定のルールは軽くクリアできる。
これは早い話、合法的な租税回避だが、この富裕層だけにできる租税回避のスキームはすでに横行しているきざしが見える。





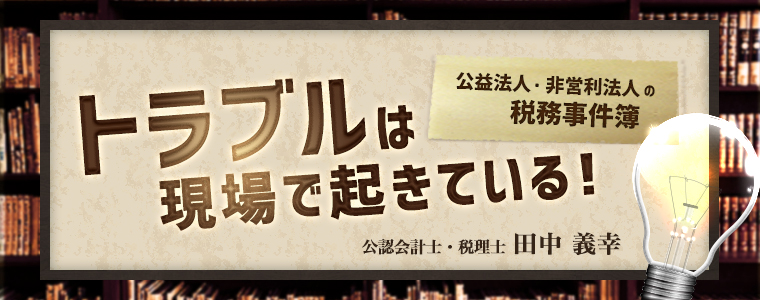




 無料登録はこちら
無料登録はこちら