社長貸付金・社長借入金消去の税務 ~証拠の論点も踏まえて~55
2025/08/25
・売買契約書
0円譲渡の場合、1円備忘価額で譲渡します。この1円は通帳間を通します。これにより通帳記録という証拠の補完になります。
○譲渡の対抗要件
株主名簿への記載(会社法130)が前提となるため、
→(証拠)
・株主名簿
・名義書換請求
・法人税別表第二
・・・→ただしこれはあくまで補完という位置付けになります。
○閉鎖会社
株主総会・取締役会承認(会社法139)
→(証拠)
・譲渡承認請求書
・株主総会議事録
・取締役会議事録
各議事録の署名や押印に係る留意点はシリーズ<法人編>で解説しています。新株発行の場合、株式の引受けに係る証拠保全は下記が代表的です。
○新株の募集:株主総会or取締役会の決議(会社法199 ~ 201)
→(証拠)
・株主総会議事録
・取締役会議事録
○新株の引受け:会社への申込み、総引受契約(会社法203、205)
→(証拠)
・申込書
・引受契約書
○新株の割当て:株主総会・取締役会の決議、総引受契約書(会社法204、205)
→(証拠)
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・総引受契約書
○払込み:現実の出資(会社法208)
→(証拠)
・振込みによる資金移動
税実務では現金手渡しは証拠力を有しない、と考えます。
・法人税申告書該当箇所
・・・→ただしこれはあくまで補完という位置付けになります。
なお、上記全般で、各契約書、各申込書などは、自署又はその人による押印が原則として必要です。各法で特段の定めがない場合においてもそうすべきです。代筆、判子の使い回し、判子の押印代行は証拠としての価値を著しく落としますし、本人の記憶にも残らない可能性が高いため、当局調査における聴取書での供述記録が不整合になり得ます。
名義財産について当局調査における当局側のエビデンスに対する考え方について教えてください。
〇その他行政文書 調査に生かす判決情報020
情報 調査に生かす判決情報issued;020 平成21年6月 他
人名義財産の帰属の判断基準-財産の名義人がその財産を管理運用していたとしても、その財産が名義人に帰属するとは限らない-東京地裁平成20年10月17日判決(国側勝訴・相手側控訴)東京高裁平成21年4月16日判決(国側勝訴・確定)
(今号のポイント)
▼ 財産の帰属の判定上、その財産を誰が管理運用していたかは、判定の一要素にすぎない。ある財産が誰に帰属するかの判定は、「裁判所の判断のポイント」に記載している①から⑤等を総合勘案して、財産の名義人がその財産を自己の財産として完全に支配管理し自由に処分できる状態にあったかどうかにより判断する。したがって、財産の帰属の判定上、財産の管理運用を誰がしていたかということは重要な要素ではあるが、判定上の一要素にすぎないのであり、これを殊更重視する必要はない。
▼ 調査において信用性の高い証拠を収集することが、課税処分をする上で有効であり、その後の不服申立てや訴訟の重要な鍵となる。裁判所は、訴訟当事者が証拠により立証した事実を基に課税処分の適法性を判断することになる。したがって、裁判所がどの証拠を基に判断するかによって、判決内容は大きく異なることになるから、裁判所が判断材料とする証拠、すなわち、信用性の高い証拠によって国側の主張を立証する必要がある。そして、信用性の高い証拠の収集は、調査段階において、納税者の主張を覆す材料等になり得るし、それらの証拠をどれだけ収集したかが、以後の不服申立てや訴訟の重要な鍵となる。
(事件の概要)
本件は、平成13年4月に死亡した被相続人甲の相続人である原告ら(被相続人の子)が、相続税の申告をしたところ、Y税務署長から、申告において税額の計算の基礎とされなかった甲の妻乙名義の財産の一部が、甲の遺産であるとして、相続税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため、原告らが、更正処分等の取消しを求めて提訴した事件である。
(争 点)
乙名義の預金等は、相続開始時において甲に帰属する財産か否か。
(相手側の主張の概要)
一般に、財産を取得する者は自己の名義でその取得及び管理をするものであるから、財産の帰属先を判定する上で、財産の名義は極めて重要な要素であるところ、乙名義の預金等の取引手続はすべて乙が行っていたことなどからすれば、乙は乙名義の預金等を自ら管理運用していたといえるから、乙名義の預金等は相続開始前から乙に帰属していた財産である。
(国側の主張の概要)
ある財産が誰に帰属するかは、当該財産の①購入原資の出捐者、②管理運用の状況、③収益の帰属者及び④名義人と管理運用者との関係等を総合考慮して判断すべきであるところ、乙名義の預金等の取引の手続は甲の指示により行われ、また、甲の同意がなければその運用をすることができなかったことなどからすると、乙名義の預金等は相続開始時において甲に帰属していた財産(※下線筆者)である。





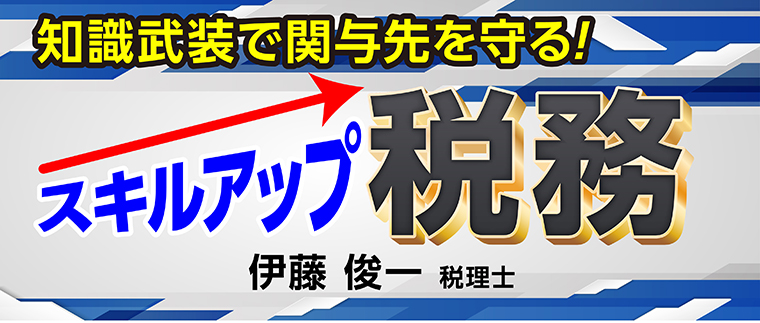




 無料登録はこちら
無料登録はこちら