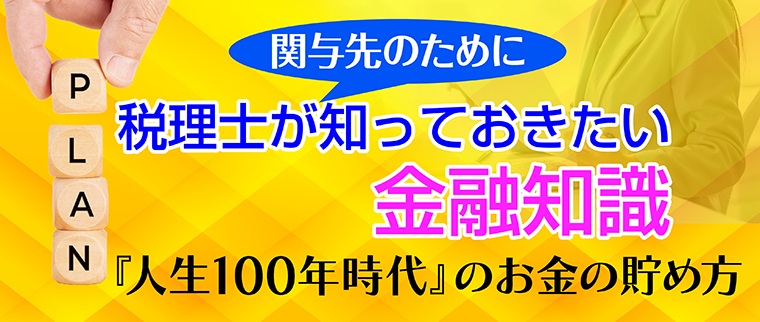金融商品のきほん-その⑧「NISAやiDeCo、どちらを先にする?」
2025/04/22
新年度がスタートし、投資を始めてみようという方もいらっしゃるのではないでしょうか。中でも、はじめて投資をする社員の皆様からは、「NISAとiDeCo、どちらが先がよいですか?」というお声がよく聞こえてきます。そこで、今回は新NISA(以下「NISA」)とiDeCo(イデコ)について見ていきます。
■「NISA」と「iDeCo」は、どう違う?
NISA(少額投資非課税制度)とiDeCo(個人型確定拠出年金)は、どちらも税金が非課税になる「税メリット」がある制度です。それぞれの特徴を見てみましょう。
《NISA》
NISAは、少額の投資が非課税になる制度で、口座数は2,560万口座、買付額は17兆円超です(2024年12月末現在)。NISAで投資できる金融商品は、株やETFの他、はじめて投資をする方向けの手数料も安い投資信託などが対象です。NISAには「つみたて投資枠」と「一括投資枠」がありますので、毎月少額をコツコツ投資することも、まとまった資金を一括で投資することもできます。
NISAは最高1,800万円まで非課税で運用することができるため、まとまった資産づくりに適しています。
「もし、途中でお金が必要になったら、どうしよう・・・」とご心配の方も多いですが、NISAは途中で引出しすることができます。そのため、老後資金だけでなく、教育資金や住宅資金にも活用できます。
《iDeCo》
iDeCoは、老後資金づくりに適した制度で加入者数は358万人です(令和7年1月現在)。iDeCoは自分で掛金を支払い(拠出)、自分で運用する制度です。65歳になるまで掛金を積み立てできるので、公的年金と同様にコツコツ老後資金を積み立てることができます。 また将来受け取る場合は、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
このように、iDeCoは原則60歳になるまで資産を引き出すことはできません。そのため、しっかり老後資金を準備するための制度だと言えます。
iDeCoは掛金の支払時・運用時・受取時に税メリットがあります。掛金の支払時は全額非課税、運用時は非課税、受取時には一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金なら公的年金等控除が適用できます。
NISAは少額から、ライフプランに合わせた資産づくりができます。確実に年金づくりを目的とするならば、iDeCoなら途中で引き出せません。しかも、税メリットが大きいと言えます。
iDeCoの掛金を月2万円支払った場合、所得税と住民税の税率が20%なら、4万8,000円税金が安くなります。
iDeCo の掛金 毎月2万円×12月=年間24万円・・・全額所得控除
24万円×20%=4万8,000円
(税率が30%の場合、24万円×30%=7万2,000円)
10年掛けるなら48万円、30年なら144万円になります。年収が増えれば税率も高くなりますので、節税効果はより増えます。
【NISAとiDeCo】
|
|
NISA |
iDeCo |
|
対象年齢 |
18歳以上 |
原則20歳以上65歳になるまで |
|
非課税 |
最高総枠1,800万円まで非課税 配当金や売却益などの運用益は非課税 |
掛金支払時:全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除) 運用時:非課税 受取時:一時金なら退職所得として退職所得控除、年金なら公的年金等控除 |
|
途中引出し |
いつでも可 |
原則60歳まで払い出しできない |
|
口座手数料 |
無料 |
口座開設手数料や管理料がかかる |
■「NISA」と「iDeCo」をどう使う?
どちらも税メリットのある制度ですが、どう使いわけたらよいか一般的なケースで考えてみましょう。
■20~30代の方
20~30代の方は、これから教育資金や住宅資金の計画が控えています。そこで、NISAを優先して貯めることを検討します。ただし、教育資金や住宅資金は絶対に使う資金です。全額NISAでというのは、リスクがあります。必要な時に値が下がることもありえます。「税金が高くて・・・」という方なら、余裕に応じてiDeCoを検討してもよいでしょう。ただし、60歳まで引出しできないため掛金はムリなく、口座管理料等の手数料は事前に必ず確認しましょう。
フリーランスや経営者の方なら、iDeCoの他に、小規模企業共済に加入する選択肢もあります。
■40~50代の方
40~50代の方は、iDeCoを優先して検討します。収入も増えたが、教育費や住宅ローンの負担もある時期ですが、ここでしっかり老後資金を貯めておきましょう。iDeCoの税メリットで税金を減らす効果も期待できます。その分、貯金に回して、NISAで運用することもできます。
■まず、「貯まる体質」になる
これから投資をはじめる方や新入社員の方の場合、まず「貯まる体質」になることをおすすめします。「貯まる体質」とは、黒字家計で、かつ、貯金ができることです。最初は、病気などで働けなくなったときでも自分や家族を守ってくれる緊急予備資金(毎月の3~6ヵ月分)を貯めていきます。ただし、ムリは禁物です。はじめは毎月1,000円でもよいので貯めクセをつけていきましょう。NISAは金融機関によっては、100円からでもできます。
知識を味方に、上手に制度を活用していきましょう。
アドバイザー/中島 典子 税理士
社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー(日本FP協会 CFP®認定者・1級ファイナンシャルプランニング技能士)
公益財団法人日本数学検定協会 ビジネス数学インストラクター、住宅ローンアドバイザー
一般社団法人相続診断協会 相続診断士
【主な著書(共著含む)】
『会社が知っておきたい 補助金・助成金の申請&活用ガイド』(大蔵財務協会)
『ムダなく、ムリなく、かしこく 資産づくりのキホン』(清文社)
『定年前後の手続きガイド』(宝島社)、『金持ち定年、貧乏定年』(実務教育出版)など多数。
中島典子先生ご出演のYouTubeはこちら!