変わる! 公益法人会計基準 現場の経理担当者への影響は?
2025/07/29
田中 義幸 公認会計士・税理士
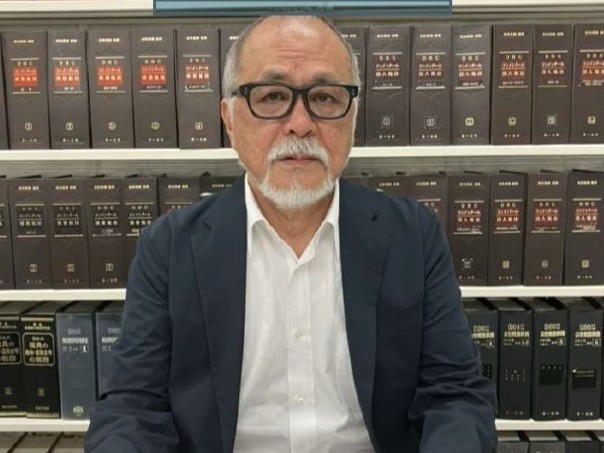
今年4月、新しい公益法人会計基準の適用が始まった。15年ぶりの改正は会計の考え方や見せ方に大きな転換をもたらしている。3年間の猶予期間はあるものの、現場では対応に向けた緊張感が高まっている。具体的にどのような影響があるのか、公益法人支援に特化した田中義幸公認会計士・税理士に話を聞いた。
——公益法人会計基準が改正された経緯について教えてください。
今回の公益法人会計基準の改正は、2008年の制度改革以降、約15年ぶりの大きな見直しとなりました。背景には、これまでの公益法人の貸借対照表(BS)や正味財産増減計画書(PL)は、公益法人の特殊性・固有性を反映していたため、一般企業の財務諸表と比べて外部の関係者には「分かりにくい」との指摘があったことがあります。そこで、公益法人の財務諸表の透明性や分かりやすさを向上させるため、一般企業のBS・PLに近づけるかたちで今回の改正が行われました。
——外部の関係者とは、たとえば会員や寄附者などでしょうか。
はい。前回の平成20年版の会計基準では、その目的について「この会計基準は、公益法人の財務諸表の作成に関し、その基本的な考え方を明らかにし、かつ、法人間の会計処理及び財務諸表の表示の統一を図ること」と、わずか2行で示されていました。しかし、今回の令和6年改正では、目的に関する記述が2ページにわたり、その中でも特に注目されるのが「資源提供者」という言葉です。公益法人に対して会費を負担したり、寄附などを行う人のことですが、この言葉が15回も登場しています。そこには、これまでの会計基準では「資源提供者」に対する情報開示が十分ではなかったという認識のもと、今回の改正により使い道や成果をより分かりやすく示すことが強く打ち出されていることが読み取れます。
——外部から見ても分かりやすいBS・PLになったと思われますか。
一般企業に合わせてBS・PLを簡素化した結果、公益法人の特殊性・固有性の情報がBS・PLから除外され、すべて「注記」の中で記載することになりました。これまで公益法人の会計は、BS・PLが中心の「主」で、注記はそれを補足する「従」の関係だったのが、新しい会計基準では注記が「主」となり、BS・PLが「従」の関係になったと感じています。従来の公益法人会計基準に慣れ親しんできた人でも、簡素化されたBS・PLを見ただけでは、その法人の実態をつかむことは難しいと思います。現場の実感としては、BS・PLの簡素化と引き換えに、注記が複雑になって作成の負担が増したような気がします。
——具体的にどのような点が複雑になったのでしょうか。
例えば、従来の公益法人の会計では「公益目的事業会計」、「収益事業等会計」、「法人会計」という3つの会計区分を設けていましたが、新しい会計基準では、これに加えて、それぞれの会計区分ごとに「財源区分」を明示することが求められるようになりました。つまり、これまでの「勘定科目×会計区分」の2次元(2つの軸)の区分で済んでいたものが、「勘定科目×会計区分×財源区分」という3次元(3つの軸)の処理が求められるようになったわけです。これは非常に煩雑で、ソフトメーカーも頭を悩ませていると思われます。内閣府の資料でも、「会計区分フラグ」と「財源フラグ」の両方のフラグを設定するように求めています。
——この新基準は、どのような法人に適用されるのでしょうか。
新しい会計基準が義務付けられるのは、全国で約1万ある公益社団法人・公益財団法人と、約5千から6千の移行法人です。移行法人とは、旧社団・財団法人が公益認定を受けずに一般法人に移行し、公益目的財産を計画的に使うことが義務づけられている法人です。また、今後新たに公益認定を受ける法人も、新しい基準の適用を受けることになります。
—— 一般社団法人などは対象外ですか。
はい。もともと従来の「公益法人会計基準」自体が、一般社団法人・一般財団法人には任意の適用だったので、新しい会計基準も義務ではありません。ただ、従来の会計基準は使いやすさもあり、多くの一般社団法人などで採用されてきました。では、新しい会計基準に任意で移行するかというと、慣れ親しんできた会計基準の全面的な切り替えとなるほか、ソフトの入れ替えなどで費用も発生しますので、特に小規模な法人では「現状維持」を選ぶところが多いと考えられます。国としては、新しい会計基準に移行を促したいという意向があるようですが、実際にはハードルが高いと感じるところが多いでしょう。
——なぜ、国は移行を促していると感じられるのでしょうか。
内閣府が公表している公益法人会計基準のFAQにおいて、一般社団法人などが利用している旧会計基準については、「今後メンテナンスしません」と明記されています。これはつまり、「今後は更新のない古い会計基準を使い続けることになりますよ」というメッセージを通じて、やんわりと新基準への移行を促していると読み取れます。
——公益法人を支援する税理士事務所にも影響がありそうですね。
はい。知り合いの高齢の税理士の中には、「新しい会計基準には対応できない」として、顧問先の公益法人を別の税理士に引き継ぐケースも出ています。一方で、これから公益法人支援に注力したいと考えている若手の税理士にとっては、今回の改正がビジネスチャンスになり得ると思います。今後、一般社団法人の中にも、新しい会計基準への移行を選択するところが出てくる可能性がありますので、公益法人会計基準に精通する税理士として、自身の専門性をアピールする絶好の機会ともいえるでしょう。
★田中先生も講師を務めるオンデマンド研修では、NPO法人・公益法人・社会福祉法人など非営利法人の会計・税務に関する実務対応を効率的に学ぶことができます。ぜひこの機会にご活用ください!
こちらから⇩





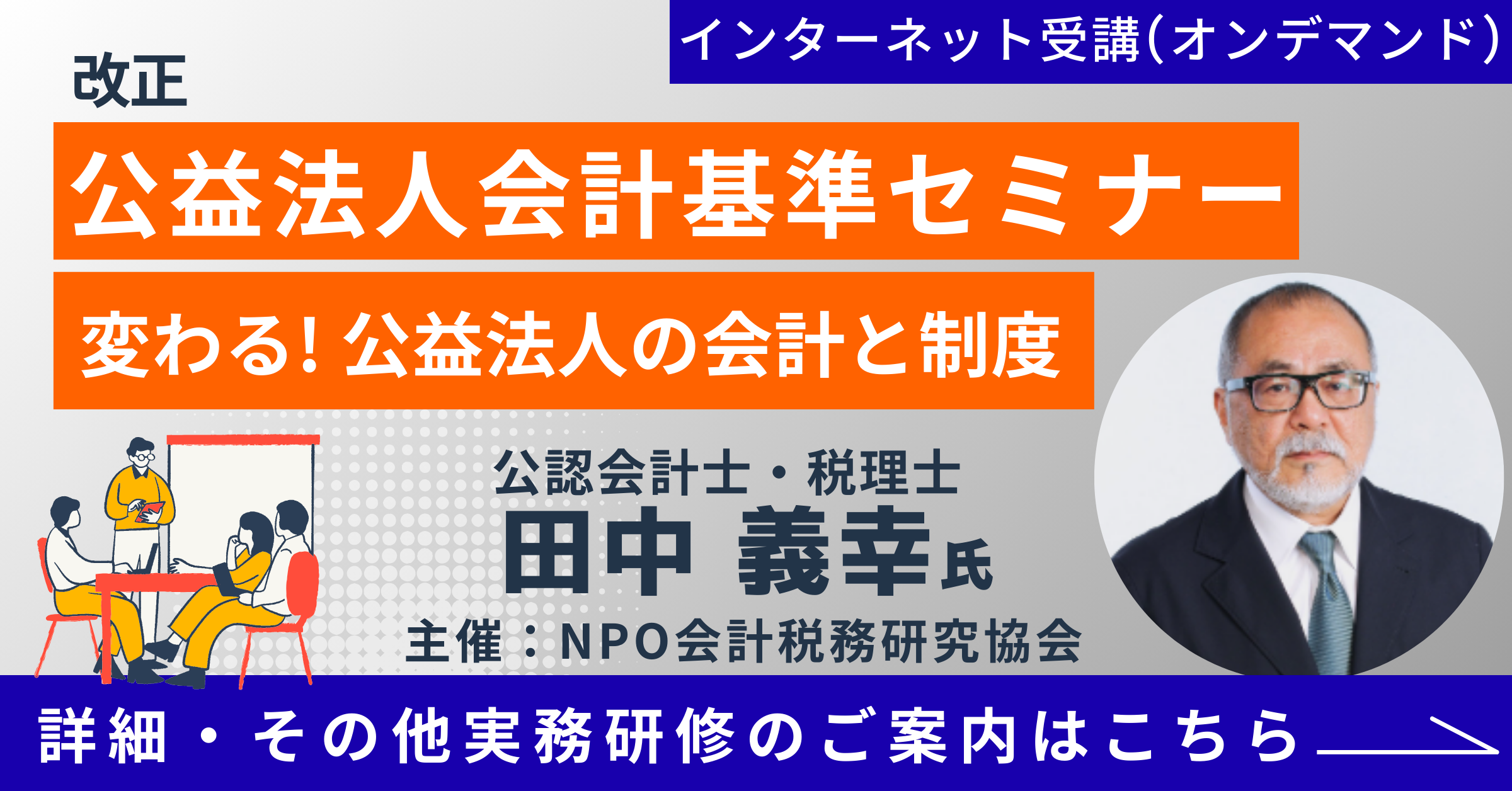




 無料登録はこちら
無料登録はこちら