長年の想いを託して伝えたい制度 特別障がい者の将来を守る 「特定贈与信託」
2025/11/04
北田 全基 税理士
(大阪・大阪市)
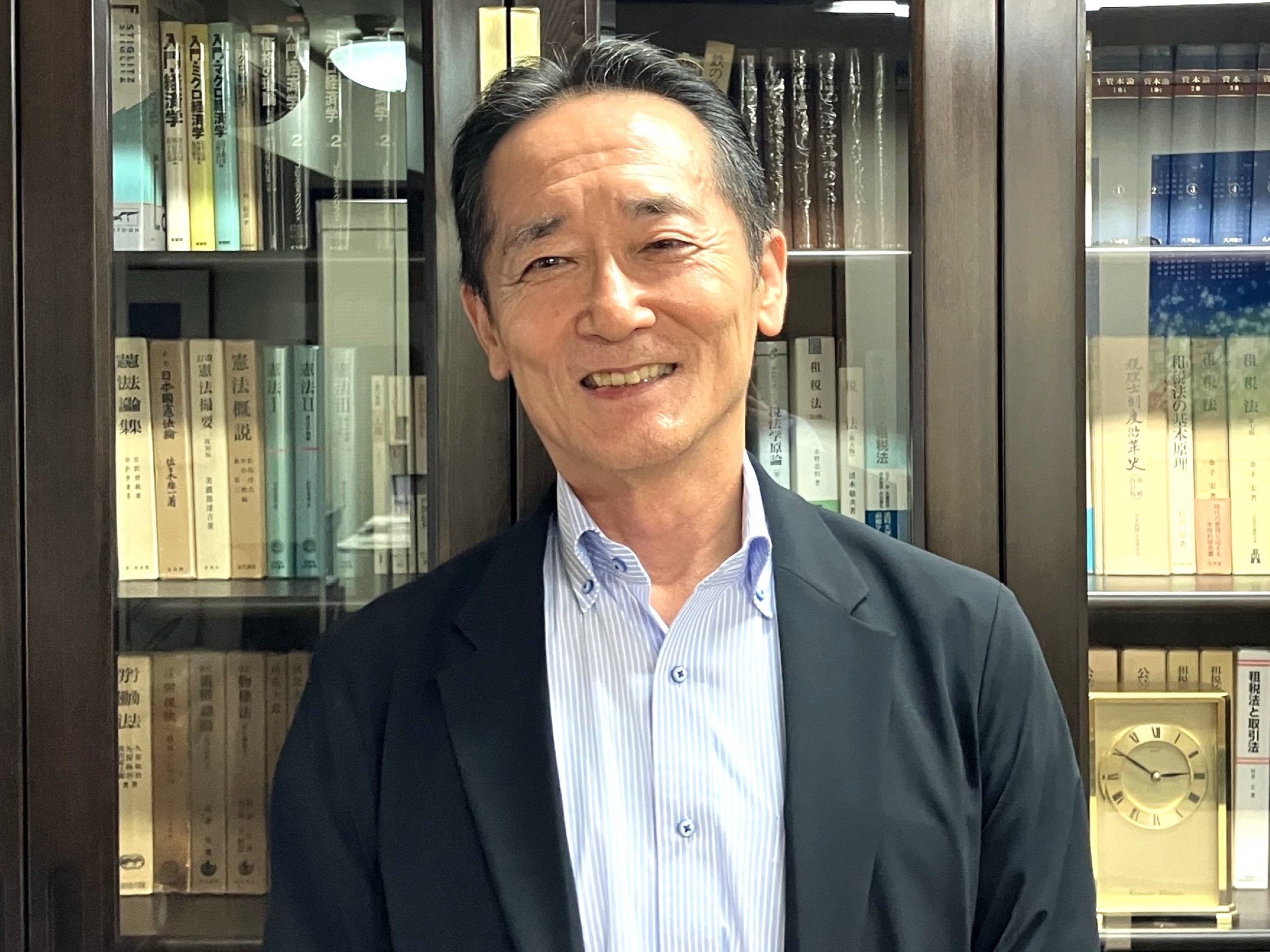
北田全基税理士が開業当時から注目してきた「特定贈与信託」。一定の障がい者の「親なき後」を支えるために設けられた仕組みだが、制度創設から今年で満50年にもかかわらず、その存在は税理士の間でも十分に知られていないのが現状だ。実務を通じて支援にも携わってきた北田全基税理士に、この制度へ寄せる想いを聞いた。
――税理士試験の受験時代から障がい者に関する税制に関心を持たれていたそうですね。
昭和54年から税理士試験の勉強を始めましたが、受験科目であった相続税法のテキストで相続税法21条の4の「特別障害者に対する贈与税の非課税」制度を知りました。この制度は、昭和50年度税制改正で創設されたもので、障がい者の長期的な生活保障に配慮した、非常に優れた仕組みだと感じました。一定の障がい者の生活保障をより手厚くするため、3000万円(立法当時)までの信託受益権の贈与は非課税となるこの制度を知ったときは、「これは本当に良い制度だ」と感心したのを覚えています。
――具体的には、どのような制度なのでしょうか。
特別障害者を受益者とする信託を設定した場合、その信託財産の信託受益権のうち3000万円までは贈与税が非課税となります。従来の障害者控除が相続時の税額軽減に限られていたのに対し、この制度は生前に信託を通じて財産を安全に管理・給付できるのが大きな特徴です。親なき後に備え、生前から長期的な生活保障を準備できる仕組みが誕生したことは、非常に意義深いと感じました。しかも、昭和63年度税制改正により、非課税限度額が3000万円から6000万円に拡充され、さらに平成25年の税制改正では適用対象となる障がい者が「特別障害者」から「特定障害者」に改められ、制度の幅が大きく広がっています。
――非課税限度額が倍増されたのは大きな改正ですね。
はい。障がい者の方の平均寿命も伸び、医療や介護にかかる費用も年々増えています。そのため、従来の3000万円の限度額では将来の生活に不安を感じていたご家庭も少なくなかったと思います。非課税枠が6000万円に拡充されたことで、制度の実効性が高まり、障がい者ご本人の生活保障もより厚くなったといえます。
――税理士登録されてから、この制度を活用する機会はありましたか。
特定贈与信託を提案する場面はなく、制度の存在すら忘れかけそうな時期が続きました。そんな中、10年ほど前に大きな転機がありました。顧問先の社長に障害者手帳をお持ちであるお嬢さんがいることを知ったのです。
――どのような経緯で気づかれたのでしょうか。
関与当時、お嬢さんは結婚されていて社長の扶養親族に入っておられず、私も把握できていませんでした。その後、社長の会社の経理担当者として勤務されることになり、その際に提出された扶養控除等異動申告書から、そのお嬢さんが特別障害者であることを知ったのです。そのとき、以前からその社長が「自分も高齢だから、そろそろ相続税対策を考えないといけない」と話されていたことを思い出し、頭の片隅にあった特定贈与信託の非課税制度がよみがえりました。そこで、社長に「相続対策として特定贈与信託という素晴らしい制度があります。信託銀行に相談されてみてはいかがでしょうか」と伝えました。
――信託銀行などに相談には行かれたのでしょうか。
社長はとても忙しく、結局、信託銀行に足を運ばれることはありませんでした。その後も特定贈与信託について繰り返し情報をお伝えしましたが、なかなか動きはみられませんでした。そうした中、不動産仲介で日頃からお付き合いのあった日税不動産情報センターの担当者が事務所を訪れ、日税グループに「日税信託」という会社が加わり、信託業務を始めたことを知りました。日税不動産情報センターは、どんな案件でも誠実に対応してくれる信頼できる会社ですので、そのグループ会社である日税信託なら安心だと思い、社長に「一度相談されてみてはいかがですか」とご提案しました。
――今度は動いていただけたのでしょうか。
しばらくして社長に確認しましたが、まだ日税信託に連絡されていませんでした。これまでであれば、社長が動くのを待ったかもしれません。しかし、特定贈与信託は本当に優れた制度で、お嬢さんの将来のためにもぜひ利用していただきたいとの思いから「社長、これは早く進めましょう」と強く背中を押しました。その後、社長は日税信託の担当者と面会され、もともと信託の基本的な知識をお持ちだったこともあり、手続きはトントン拍子に進み、無事に契約まで至りました。契約後、社長にも喜んでいただき、私自身もご提案して本当に良かったと思いましたね。
――日税信託の対応はいかがでしたか。
例えば、信託のスキームについて「こういうことは可能ですか」と質問すると、日税信託の担当者は信託協会に確認をした上で、後日「そのスキームは難しいと思います」と責任ある回答をしてくれました。その場しのぎの返答ではなく、誠実に対応していただけるので、とても安心して任せられると感じています。すでに、別のお客様についても相談しています。
――障がい者を取り巻く環境も変わってきたと思われますか。
今でこそ、家族に障がい者がいることをオープンにしやすい社会になりましたが、昔は障がい者に対する世間からの偏見等もあり、口に出すことをはばかる方も多かったと思います。税理士として、そうした事情に気づいたら、特定贈与信託の制度を紹介し、支援につなげることが大切だと考えます。そのためにも、税理士自身が特定贈与信託についてもっと理解を深めることが必要だと思います。
――特定贈与信託はあまり知られていないのでしょうか。
残念ながら認知度は高くないと思います。贈与税の非課税といえば、住宅取得資金のほか、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与などはテキストや解説書に書かれていますが、特定贈与信託についてはほとんど触れられていません。そもそも贈与税は相続税の補完税という位置づけで、研究対象にする人も少なく、その中でも特定贈与信託となれば、取り上げられることは少ないでしょう。だからこそ、日税信託には特定贈与信託の普及のために、積極的に情報発信してほしいですね。
――お話を伺って、北田先生の特定贈与信託に対する熱い想いが伝わってきます。
特定贈与信託は節税対策と捉えられることもありますが、私は保険や不動産を活用した節税には、自分の税理士のスタイルとして抵抗があります。顧問先の社長から要望されれば、日税グループの保険会社などを紹介することもありますが、私から積極的に勧めることはありません。ただ、特定贈与信託だけは別です。障がい者の方にとって極めて意義のある制度であり、私自身の長年の想いも込められています。この制度だけは必ずお伝えしなければならない――、そうした使命感を持って取り組んでいます。



