医療法人承継を円滑に導く 認定医療法人制度と税理士の役割
2025/10/23
藤澤文太税理士事務所
藤澤 文太 税理士
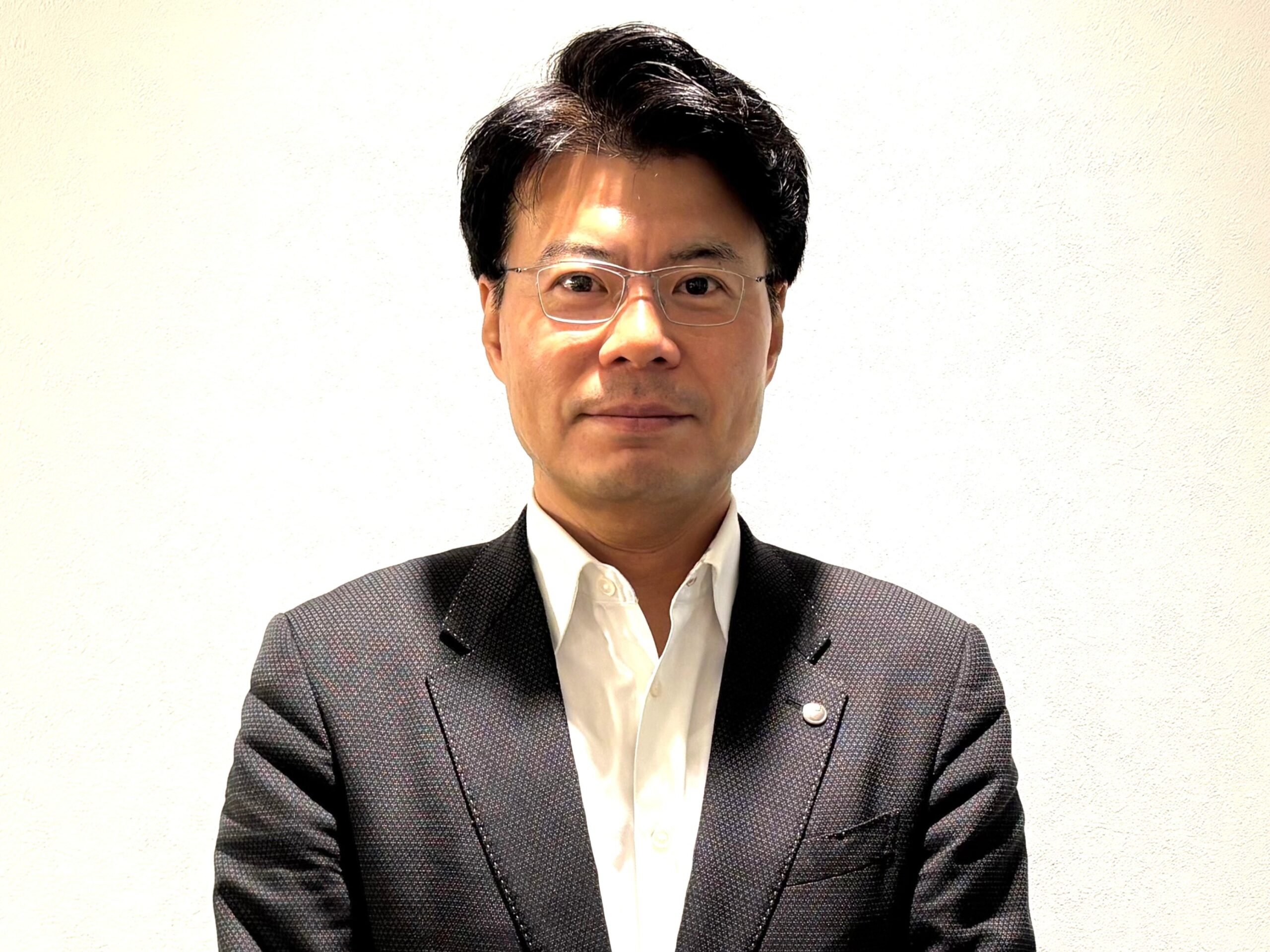
持分あり医療法人は、出資持分が財産権とされるため、承継時に多額の相続税や贈与税が発生するほか、払戻請求リスクによって法人の存続や地域医療の継続に支障をきたす恐れがある。こうした課題を解消するために創設されたのが「認定医療法人制度」だ。だが、制度開始から10年が経過した今も活用は十分に進んでいない。
こうした状況に、病院の税務会計顧問をはじめ数多くの医療法人承継に携わってきた藤澤文太税理士は、「実は税理士先生にもリスクとなる側面があります」と警鐘を鳴らす。
――まず、認定医療法人制度が創設された背景からお聞きします。
医療法人は本来、営利を目的としない存在ですが、出資持分がある場合には解散や払戻しの際に出資者へ残余財産が分配される仕組みがあり、実質的に営利法人と同じ性格を帯びてしまいます。そこで、国は医療法人の非営利性を徹底するため、出資持分ありの医療法人から出資持分なしの医療法人への移行を促したいと考えていました。しかし、強制的に移行させることは憲法上、財産権の侵害にあたります。そこで、厚生労働省は税制優遇をインセンティブとして、平成26年に「認定医療法人制度」を創設しました。
――どのような税制上のメリットがありますか。
最大のメリットは、持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行する際の課税が、要件を満たせば実質的に非課税となる点です。認定を受ければ、相続や事業承継の際に発生する多額の相続税負担や、出資者からの払戻請求リスクを回避することができます。
――現在の利用状況を教えてください。
令和7年3月末時点で、全国の医療法人は5万9419法人。そのうち持分ありが3万5766法人あり、依然として約6割を占めています。制度創設時には約4 万1000法人でしたので5000件ほど減少しましたが、大半は廃業によるものです。
実際に認定医療法人制度を利用した件数は令和6年末時点で累計1142件にとどまっています。廃業の背景には、経営者の高齢化や後継者不在が大きく影響しています。親族内承継や第三者承継は医療法人を存続させ、地域医療を守る大きなカギとなりますので、厚生労働省としては、今後さらに同制度の活用を促していきたい考えだと思います。
――なぜ、あまり利用が進まないのでしょうか。
最大の理由は制度の認知度不足です。特にクリニックではその傾向が顕著で、「そんな制度があるの?」という反応がほとんどです。一方、病院ではすでに活用が進んでおり、認知度の差がはっきりしています。
――病院とクリニックで認知度に差が出る理由は?
病院は借入額も大きいので銀行が深く関与します。その過程で大手税理士法人やコンサル会社を通じて制度に関する情報が自然と入ってきます。しかし、クリニックはそうした関わりが少なく、情報が届きにくいのが現状です。ただし、クリニックでも出資持分の評価が高く、承継時に多額の税負担が生じるケースも少なくないため、制度活用を検討する視点が求められます。
――顧問税理士の役割についてどのようにお考えですか。
事業承継はドクターにとって最も重要な課題の1つです。そのため、信頼できる専門家からの情報でなければ耳を傾けてもらえないのが実情です。知らない業者から提案されても受け入れられにくいでしょう。だからこそ、クリニックのドクターにとって最も身近で信頼できる顧問税理士が、この制度の活用を見極め、提案ができるかどうかが、医療法人の承継リスクを左右するポイントになると考えています。ただ、制度の名前は知っていても実際に案件を扱った経験がある税理士先生は少なく、十分に提案されていないのが現状です。また、制度の提案をためらう方もいらっしゃいます。
――なぜ、ためらうのでしょうか。
理由は2つあると思います。1つは持分をなくすことは財産を手放すことになるため「もったいない」と考える税理士先生が一定数いらっしゃること。もう1つは、認定を受けるためには8つの要件を満たし、それを6年間維持しなければならない点です。法人によっては負担が大きく、維持できなければ遡及課税のリスクもあるため「やめておいた方がいい」と判断する先生も少なくないのです。とはいえ、私の経験上、制度について正しくご理解いただいたお客様の中で持分に固執される方はほとんどいません。認定を受けた法人はいずれも「承継に役立った」と評価しています。8要件についても、認定を受けた法人で要件維持ができず取り消しになった例はこれまで1件もありません。
――実際に制度を活用された事例を教えてください。
地方で何十年も前に設立された持分ありの医療法人のケースでは、父親が整形外科クリニックの院長を務め、息子さんが医学部を卒業し承継に戻ってくる、よくある親子承継の形でした。息子さんは大学病院で経験を積み、高い医療技術を持って帰ってきたので患者さんがどっと増え、経営もさらに好調になりました。ただ、出資はすべて院長である父親が持っており、もともと1000万円だった出資が、院長と息子さんの努力で評価額が7億円に膨らみました。その結果、相続時には3億円の相続税が発生する見込みとなり、息子さんは大きな負担に直面しました。ご自身で調べる中で認定医療法人制度を知り、顧問税理士へ相談されました。最終的にその顧問税理士を通じて私のもとへサポートを求められたというのがこのケースの経緯です。
――移行はスムーズに進みましたか。
親子承継では経営方針が合わず、親子喧嘩のようになってしまうことも少なくありません。このケースでも息子さんが「もう自分で新しい法人を作ろうか」と悩むほどこじれていました。ところが、制度のことを丁寧に説明し、院長にもご理解いただいたことで認定を取得でき、納税リスクが解消されました。結果として親子で前向きに経営を続ける道が開けたのです。特に印象的だったのは息子さんが頑張れば頑張るほど膨らむ税金という足かせから解放され、「これで安心して医療に打ち込める」と喜んでいたことです。
――持分なしの医療法人への移行について、ほかの税理士先生から相談を受けることはありますか。
多いですね。認定医療法人制度は専門性が高く要件も厳しいので、提案のハードルが高いと感じる税理士先生は少なくありません。説明の難しさや実績の少なさから手を出しにくく、結果として一人で抱え込んでしまったり、検討を後回しにしてしまうケースも見受けられます。その結果、顧問先にとって将来の不利益につながることもありますので、そこは注意したいところです。
――多額の相続税などがかかるということでしょうか。
はい。制度を利用しなかったことで、承継の際に多額の相続税や贈与税が発生することになれば、「なぜ制度の説明がなかったのか」と疑問や不満が生じる可能性があります。場合によっては損害賠償責任を問われることにもなりかねません。また、代替わりのタイミングでは顧問契約を見直すケースがありますが、新しい院長先生に、「重要な制度を提案してもらえなかった」という印象が残れば、せっかく築いてこられた信頼関係が途切れてしまう恐れも考えられます。
――最後にメッセージをお願いします。
認定医療法人制度は、まだ十分に認知されているとは言えません。だからこそ、身近な存在である顧問税理士が正しい情報を伝えることは、とても重要な役割だと考えます。ただ、すべてを一人で抱える必要はありません。医療に専門分野があるように、税理士にも得意分野がありますので、協力し合うことで顧問先にとって最も有益な承継を実現できると考えます。









 無料登録はこちら
無料登録はこちら