総則6項について
2025/10/30
昨今、「総則6項」と騒がれて久しいですが、少し整理したいと思います。
1 総則6項とは
租税法律主義を採用する現在の日本では、財産の評価については、相続税法22条の定めがあります。具体的には、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は当該財産の取得の時における時価による。」とされ、ここでいう時価については、課税実務上、国税庁の定める評価通達によることが行われています。通達とは、本来、行政官庁の上位の機関が下位の機関に対し、事務についての指示や命令をまとめた文書であります。法的な拘束力はありませんが、評価の実務においては、通達に従って財産評価をしています。これを受けて、総則1項(財産評価基本通達)において、「財産の価格は、時価による。この時価とは、課税時期において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由に取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額という。」とされ、「その価額は、この通達の定めによって評価した価額である。」とされています。
これに加えて、総則6項(財産評価基本通達)において、「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」とされ、上記、評価通達では、課税上著しく不適当な場合、国税庁長官の指示により、評価通達とは異なる評価の仕方がなされる可能性があります。
2 総則6項の影響
ここで、問題となる資産の評価は、大まかに言って、不動産と非上場株式の評価の2つに集約されます。通常、評価通達に従って、評価すれば事足りますが、ここで、通達による評価では、課税上問題があるケースが出てきます。例えば、相続直前に5億円のタワーマンションを購入し、相続税評価は、通達の通りに評価され3億円となって、遺産分割後に、やはり5億円で売却するケースなどはどうであろうか。普通に考えて、この物件の時価は、5億円ではないかという疑義が生じます。この乖離がある場合に、状況によって、総則6項が発動され、評価通達の3億円ではなく、別途国税庁が評価した5億円とされることなどが該当します。
3 令和4年4月19日最高裁判決
上記、総則6項については、様々な不服審判所の裁決や判例が積みあがってきましたが、令和4年4月19日の最高裁判決においては、課税庁側の主張を認めて、総則6項についての判断基準が示されました。ここでは、まず、相続税法22条に定める時価について、評価通達の定める方法を上回る価額としたとしても客観的な交換価値を上回らなければ、相続税法22条に違反はしないとされました。また、この場合、合理的な理由が必要とされました。そして、合理的な理由があると認められるのは、評価通達の定めによる画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合とされました。ここでは、通達評価額と鑑定評価額との間に大きな乖離があることをもって実質的な租税負担の公平に反するというべき事情があるとは言えないとしたうえで、相続税の負担が著しく軽減されるようなことを知り、かつ、これを期待して企画実行したような場合、それらをしない、あるいは、することができない他の納税者との間に看過できない不均衡を生じさせ、実質的な租税負担の公平に反するべき事情があるとされました。
4 最高裁判決を受けて、現在の事務運営指針(最終改正令和5年6月30日国税庁長官)が、改正されて、以下の内容となっております。
①評価通達に定められた評価方法以外に、他の合理的な評価方法があるか
②評価通達に定められた評価額と他の合理的な評価方法による評価額と他の合理的な評価方法による評価額との間に著しい乖離が存在するか
③課税価格に算入される財産の価額が、客観的交換価値としての時価を上回らないとしても、評価通達の定めによって評価した価額と異なる価額とすることについて合理的な理由があるか(租税回避の有無)
5 最高裁判決以降の判例
令和4年最高裁判決以降の判例では、まず、仙台薬局事件と呼ばれているものがあり、令和6年1月18日東京地裁で、課税庁が敗訴しました。こちらは、非上場株式の評価について争われ、相続前にM&Aによる売却を約束していて、相続後に、実際にそれが実行され、相続税申告時の通達評価と実際の売却額が大きく乖離していたケースで、課税庁が通達評価でなく例外的扱いをするためには、租税回避行為のような納税者側の一定の作為が特段の事情として必要であるとし、このケースでは、あたらないと判断されました。また、控訴審である令和6年8月28日東京高裁の判決でも、「特別の事情があるか否か」が争われ、単に相続後に売却が決まっていてその価額で売却されたからと言って、評価通達とは異なる評価額で評価する特別な事情にはあたらないとされました。
また、令和7年1月17日東京地裁での、課税庁の敗訴の判決における、非上場株式の評価では、株式保有特定会社に該当しないように、新株発行などを画策して、評価通達に定める株式の評価額を大きく下げていた事例でありますが、地裁は、実質的な負担の公平に反するということはできないとして、課税庁側の総則6項について認めなかった例となります。
しかしながら、この控訴審では、令和7年6月19日判決で、課税庁側が逆転勝訴しております。争点は、
①本件各更正処分価額が本件株式の客観的交換価値を上回り、本件各更正処分が相続税法22条に違反するか否か
②本件株式の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが平等原則に違反するか否か
というものでありましたが、①については、法令違反にはあたらないとされ、②については、通達評価により評価することが、実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、評価通達によらないことに合理的な理由があると認められるから、評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではない(令和4年最判)として、「租税法の一般原則としての平等原則に違反するということはできない」として、納税者敗訴となっています。
6 よって、令和4年最高裁判決で、一定の基準ができ、また、事務運営指針が発出されたことで、総則6項の発動についてある程度の予見可能性は確保されましたが、まだまだ、実務において絶対的な基準があるわけではないと思われます。ただ、意図的な節税スキームを利用して相続税の過度な圧縮を図ると危険であるということは、肝に銘じて実務を行うことが必要だと思います。
執筆:松本 次夫 税理士/監修:出岡 伸和 税理士





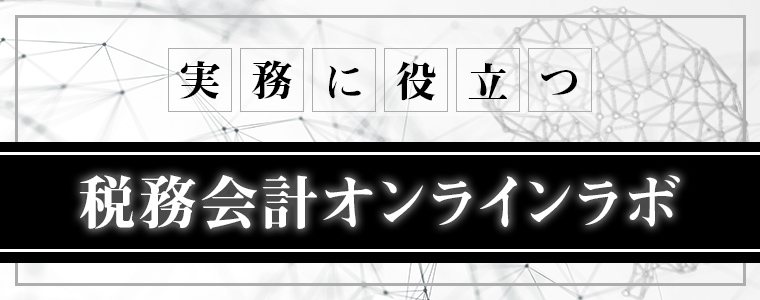




 無料登録はこちら
無料登録はこちら